|
「第1回TRMM国際科学会議」報告
初のTRMM International Science Conferenceが 2002年7月22-26日にホノルルで開かれました。 その感想やメモの幾つかを紹介させていただきます。 詳しい会議報告は「天気」2003年5月号を参照してください。運営状況:朝食代わりのパンやコーヒー、ヨーグルトの準備、肩 の力を抜いた議論を促進させるポスターセッション会 場でのフルーツやケーキの準備は評判が良かった。大 会記念品についてはペンや食事割引券などいろいろあ ったが、なかでも立派な手提げカバンが話題となった。 会場はハイアットリージェンシーホテルの脇にある会 議施設であったが、これだけ会議進行がスムーズに行 われたにも関わらず、事前にこの場所の連絡が無かっ たことに疑問を感じるものもいた。5日に渡り200件 もの発表が行われた本会議は、8時半から17時半まで という日程が主であった。併せて行われた会議も幾つ かあり、関係者は時差の影響もあって夜遅くまでくた くたの様子であったが、同じ条件でアメリカから来た 研究者は非常にタフである印象を受けたと聞いた。メ インの国際科学会議参加者の数は、1日目の午前中が もっとも多く、次第に減少し、3日目のルアウ(懇親 会)以降はそれぞれの都合や予算上の問題で帰国する 方が多くいたこともあり、ぐっと少なくなっていた。 しかし全体を通じて席の大部分が埋まっていたのは、 午前午後ともにポスターセッション後に必ず口頭発表 を入れて「帰ったらばれる」作戦が功を奏したためで あろう。またポスターセッションから次のセッション へと滑らかに移るために、ポスターセッション会場の 照明をほわんほわんと点滅させて終了を促す妙技が披 露された。これは白熱した議論に対して笑みを持って ピリオドを打つ効果抜群であり、幾人かの参加者がこ の絶妙なテクニックをメモ書きしていた。ポスターは ひとつ置きにアルファベット順に並べられ、会場は広 く余裕があった。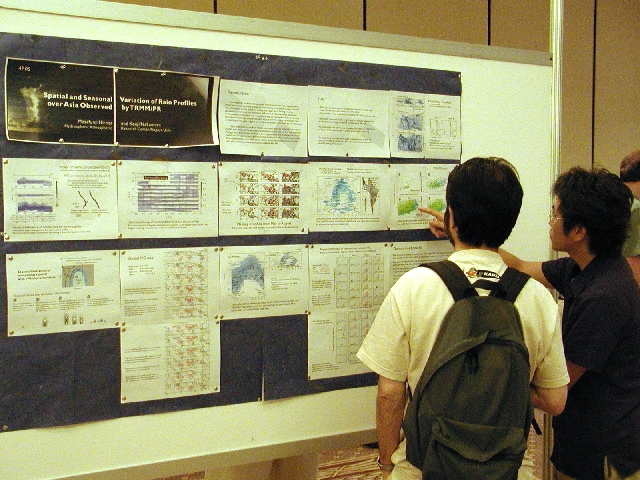
発表風景 (photo by Sato) 研究発表:多くの研究者はTRMMデータがもたらしうる成果に幅 の広い価値を感じている。潜熱推定にしても、降水精 度向上にしても、お互いの強みを持ち合って融合させ ていこうという有機的な姿勢が見られた。モンスーン や全球降水分布といった降水に関わる多くの研究者が TRMMユーザーとして集まっていたことは刺激的であ り、研究が生きたものであることを感じさせる貴重な 機会となった。様々な発表の中で私が特に興味深く聞 かせてもらったのは、3次元構造の観測がもたらした 新しい降水気候学の試みであった。ヒマラヤの跳ね水 現象、山岳性降雨、チベットやアフリカ、オーストラ リアなど(semi-)arid地域の降雨の事例解析、 RandoniaやAmazonの森林破壊域におけるメソスケー ルの循環、各種キャンペーン実験結果の比較・総括、 熱源推定アルゴリズムによる種々の降水レジームの熱 的表現、など数々の地域研究・比較研究の進展、表現 しうるパラメータの充実を感じた。また降水の3次元 構造の把握という視点が展開させた降水システムの種 類やそこに含まれる粒径分布の理解、Q1Q2などに絡め られる熱源プロファイルの推定などなど、生産的な興 味深い応用(基礎)研究の成果が多く挙げられていた。降水の地域研究(Field Experiment等)の例 交流:本滞在ではうずく放浪癖を抑え、研究者の皆さん(別 所さん他)との時間を中心として楽しく過ごさせてい ただいた。高校の大先輩・すみ先生を始めとした参加 者の皆さんから(ハワイの海を背景として)受けた刺 激は大きい。また降雨の鉛直構造について研究をされ ていたLiuや、Courtney Schumacher達に自分の研究 をじっくり話せる時間を持てたことが嬉しい。ところ でCourtneyの熱心なロビー活動は驚きであった。ほ とんどの昼ご飯を近所のサンドウィッチ屋で済ませ、 休み時間をフル活用してかなりの数の研究者と会話、 つまり就職活動をしていた。またポスター会場で、発 表でつまずいた部分についてボス(Houze)に発表の何 たるかについて説かれ、言い返し、玉砕していた様子 が暖かく記憶に残る。彼女は変わらず魅力ある先輩で あり、今後も道を交差させたい仲間に思う。反省事項:個人的な反省だが、英語を聞き取るということに依然 困難を感じる。多くの研究者に聞いてみると、完全に 分かることは困難、経験が次第に効いてくる、しかし 自然に上達するわけではない、努力を続けなさい、と いう声をいただいた。日本から来ていた若い研究者の ほとんど全てが海外経験があったり、またこれから行 く予定であるだけに生々しい意見が聞けた。まずでき ることは研究のバックグラウンドを知ること、それで かなり理解が異なると思われる。併せて意識的に関わ りあいを持つことがひとり行動の多い私にとっては課 題である。
懇親会の様子(at the Royal Hawaiian) 幾つかのキーワード(メモより)○ 全球降水分布と気候学・Houze and Schumacher: 層状性降雨の占有率は熱 源分布に深く関わりを持ち、風のvertical tiltを生 む。PRの降水タイプ識別が結果に重要なインパクトを 持つ。今後はSST等のパラメータとの関連を探り、気 候学的特徴の意味付けを深める。 ・Tao: 潜熱推定という分野の総括と見通しを述べた。 各アルゴリズムの強みと弱みのテーブルを提示。El NinoとLa Ninaという2種類のレジームの潜熱分布に 与える影響の違いを示した。比較と融合という、統一 的なプロダクトへの姿勢を打ち出した。 ・Huffman: 3時間降水量プロダクトの現況(TRMMや静 止軌道衛星を含めた複数の衛星観測値を用いた Real-timeの降水推定)の紹介。TRMMはGPCPの検証と して使える、TMIや他の衛星データが3時間降水分布 プロダクトの基となり得る、対流性降雨の割合や熱源 プロファイルなども今後考慮したい、等の成果と期待 が述べられた。 ○ 視覚的表現 ・Cyclonesの3次元構造の可視化を幾つかのパラメー タで立体図示、また水平・鉛直断面で表現した。その パラメータとは、赤外輝度温度, PRによる30dBZ等高 線、ドロップゾンデによる7.5Kの正偏差、TMI(85GHz) による氷のmoderate(200K)な散乱、TRMMによる潜熱 加熱効果、QuickSCATによる風分布などである。生ナ レーション付きのNASA製ビデオにより、熱源分布を含 めた立体的特徴を分かりやすくドラマチックに可視化 していた。 ○ 物理検証 ・Wilheit: TMIによる海の雨を検証する適当なGround Truthがこれまで無い。モデルでエラー要因の効果を 調べることを今後の検証(Physical Validation)と する。主要なエラーはその機器のFOVにおける降雨の 非一様性、つまりbeam-filling errorであり、KWAJEX やTOGA-COAREで航空機搭載レーダを用いた結果によ ると少なくとも熱帯ではその効果は安定していること が分かった。 ○ 広域に渡る地域的特徴、降水レジーム ・Negri: ランドニアにおいて、森林域では低いアルベ ド、高い粗度、深いroots、低いボーエン比、浅い境 界層、高い湿潤静的エネルギーが観測され、森林破壊 域では逆であった. ・Satoh: オクラホマで観測されたスコールライン、梅 雨、台風、浅い対流、等の異なる降水レジームについ て熱源分布の立体的表現を試みた。雲解像モデルや観 測データによる検証が今後の課題。 ・Johnsonが示した降雨イベント(MCSなど)の形に 関するorganizational modeの発展版が面白いと好評 であった。 文責‥広瀬 正史 |